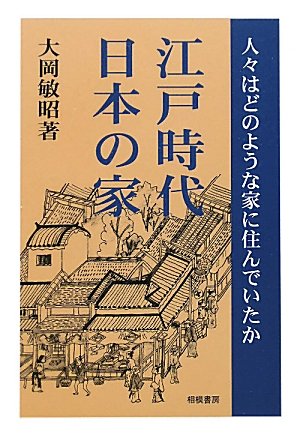住宅チラシの間取りをみて最近の住宅事情を知るのは楽しいですが、古民家の間取りにも興味があり、YouTubeで間取り動画をみて学んでいます。「江戸時代日本の家」という書籍では、現代の間取りと異なる江戸時代の間取りは、身分制度と影響があり現代の家と間取りの意味が異なるようです。
日本家屋の基礎を作った江戸時代の間取りは、現代でも通用する要素が盛りだくさんあります。
どのような部分が現代でも活かせるかを考察してみました。
土間は作業場として活用
マンションや建売住宅の間取りは仕事場スペースがありません。在宅勤務が増えて、リビングを代用している方もいるのではないでしょうか。江戸時代の土間は台所と続き、農作業などで汚れていても仕事ができる空間でした。土間は居住スペースの邪魔はしません。また、土間の空間はちょっとした用事の社交の場でもありました。私的と公的な空間にもなる便利さがあります。
動物と生活する間取り
冬は大雪が降る地方の江戸時代の間取りに顕著なのが、家畜のための空間があることです。「ウマヤ」「マヤ」という空間は土間と隣接しており、人間の居住スペースを邪魔せず、玄関近くにあります。
家の中庭の角に「ウマヤ」を設けている地域もありました。
ペットを室内で飼っているとペット専用部屋の設置場所は悩ましいところです。江戸時代の間取りが参考になるかもしれません。
襖・障子で自由に調節できる
江戸時代の公家や上級武士の間取りは部屋数が多く迷子になりそうです。
襖や障子で間仕切りしているが、襖を取り外せば大広間を作ることができたり、間仕切りすれば小さい部屋をつくることができます。そういう自由に調整できるところは、いまの家に参考にできるのではないでしょうか。
最近の開放的な間取りの家が多くなっていますが、古民家の落ち着きは現代と比較できない空間の魅力がありますね。
まとめ
江戸時代の日本の家は士農工商で間取りが異なります。地域によって特殊な屋根や間取りがあります。
今と異なる価値観で生まれた空間ですが、使える間取りかどうかは今の価値観で見ると参考になることが多いです。