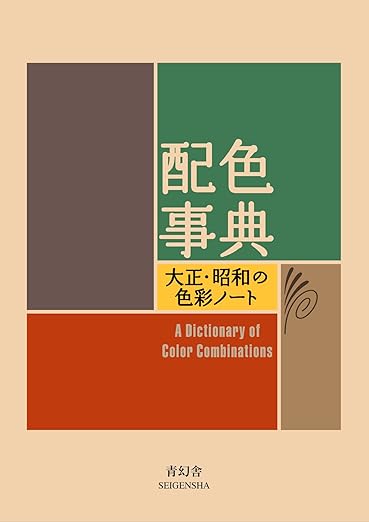海外で一部のおしゃれさんに人気の「配色事典」を購入しました。
私の購入理由は、年齢を重ねるたびに無難な色の選択が多くなってしまったからです。
もう一つの理由はマンネリの打破と、安い服でも色の組み合わせでおしゃれが楽しめるのではと思いました。
配色事典から受けた影響は服だけではありません。この本の魅力をご紹介します。
大正・昭和初期の色彩感覚はあたらしい
洋服が当たり前の時代に生まれているので、洋装の上下で色のあわせ方の参考と2色配色を読んでいると、3色から4色と展開していく本だったので最初は戸惑いました。
大正・昭和初期の本のため、着物をイメージすると納得する配色です。しかし、YouTubeの海外おしゃれさんが小物を使って4色展開の組み合わせたとき、とてもおしゃれで4色が調和していて驚きました。
洋装・和装関係ない「配色事典」の組み合わせは現代でも十分通用します。
豊かな色彩をあらわす日本語を楽しむ
「配色事典」は服の組み合わせ目的で購入したのですが、色彩をあらわす日本語が美しくて次第に読み物として楽しくなりました。
今までは色を単純に「白」「青」「赤」と大分類していましたが、「配色事典」はそんな単純ではありません。
ブルー系の”納戸色””浅葱色””花浅葱”などの色彩分類で色の世界が広がったように感じました。ほかの色彩も細かく分類されています。
豊かな日本語と色のバリエーションにふれて、日常生活にあふれる色についての意識が高くなりました。
いまでも十分活用できる良書
配色事典の大きい魅力は、自分では思いつかない色のあわせ方がたくさん掲載されていること。
色の組み合わせがどのような印象を与えるのか、客観的につかむことができます。
ファッションを例にすると、カラー診断をうけて自身の肌色とあわせやすい色彩は診断できても、色彩の組み合わせ方法の情報は不足がちではないでしょうか。組み合わせは自身のセンスを試されているような。
色と色を合わせた化学反応による印象変化は飽きることがありません。
”事典”という名のついたタイトルですが、文庫なのでコンパクトで持ち歩きやすいです。
色について興味のある方は是非手に取っていただきたい一冊です。